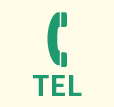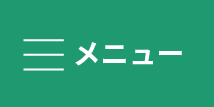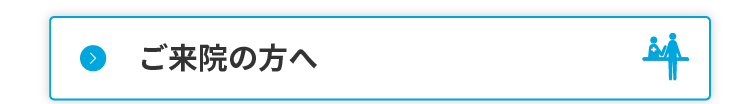目次
膵・消化管神経内分泌腫瘍・癌について
神経内分泌細胞に由来する腫瘍で、体の様々な部位から発生しますが、呼吸器や消化器(膵臓、消化管)で多くみられる病気です。
消化器に発生する神経内分泌腫瘍は、年間人口10万人あたり3-5人の発生と言われており稀少がんとされています。
悪性度に大きな違いがある2つのグループに分類されます。
- 神経内分泌腫瘍(NET:Neuroendocrine tumor)
- 神経内分泌癌(NEC:Neuroendocrine carcinoma)
NECは、NETに比べて早く進行しやすく、生命への危険も大きい腫瘍です。両者は分子学的な特徴にも違いがあることがわかってきています。そのためNECとNETでは治療方法が異なります。
治療で用いるお薬は、原発部位により少しずつ異なります。
症状
ホルモンを産生する機能性NETでは、産生されるホルモンによって様々な症状がでることがあります。一方、ホルモン産生症状のない非機能性NETでは特異的な症状はありませんが、腫瘍が増大、転移すると腫瘍の部位に応じた症状がでるようになります。
機能性NET
| 種類 | 症状 | ホルモン |
|---|---|---|
| インスリノーマ | 低血糖症状(意識障害、冷汗など) | インスリン |
| ガストリノーマ | 消化性潰瘍や逆流性食道炎による腹痛、出血、胸やけなど | ガストリン |
| グルカゴノーマ | 糖尿病、体重減少、遊走性壊死性紅斑 | グルカゴン |
| VIPオーマ | 大量の水溶性下痢、低カリウム、低クロール血症 | VIP |
| セロトニン産生腫瘍 | 皮膚紅潮、下痢、心不全など | セロトニン |
| ソマトスタチノーマ | 体重減少、腹痛、糖尿病など | ソマトスタチン |
診断
診断のために、画像検査と組織検査が行われます。
画像診断
胃カメラ、大腸カメラ、ERCP、EUSなどの内視鏡検査、CT、MRI、オクトレオスキャン、PET-CTなど腫瘍の大きさ、拡がりを調べるために適宜行います。
組織診断
腫瘍から採取された組織を用いて、NETあるいはNECの診断をします。さらにWHO2019分類(膵・消化管)を用いてGrade分類を行います。
進行度(ステージ)について
UICC TNM分類が用いられます。
- T因子 : 腫瘍の大きさ
- N因子 : リンパ節転移の有無
- M因子 : 遠隔転移の有無
によってStageが決まります。
発生した部位によりそれぞれStage分類の基準が異なります。
WHO分類2019(膵・消化管)
組織診断により、高分化型(NET)または、低分化型(NEC)に分類されます。NETはさらに細胞増殖に関連するKi-67指数、核分裂像数から(G1,G2,G3)に分類されます。治療方針や予後予測のために重要な指標になります。
| 種類 | 分類/グレード | Ki-67指数 | 核分裂像数 (/10視野) |
|---|---|---|---|
| 高 分 化 型 |
NET G1 | <3% | <2 |
| NET G2 | 3-20% | 2-20 | |
| NET G3 | >20% | >20 | |
| 低 分 化 型 |
NEC G3 小細胞型 大細胞型 |
>20% | >20 |
神経内分泌腫瘍(NETG1-G3)の治療
手術、内視鏡切除
根治を望むことができる治療です。NETの場合は、遠隔転移を有する場合(特に肝転移)でも、手術が考慮される場合が有ります。また、腫瘍を全て取り切ることが困難な場合でも減量手術を行う場合があります。
消化管NETでは内視鏡的切除できるものは内視鏡で治療をします。
局所療法(肝動脈塞栓術:TAE、ラジオ波焼灼術:RFA)
肝臓に転移したNETに対して、カテーテルを使って肝動脈塞栓術(TAE)を行ったり、針を用いて腫瘍を焼くラジオ波焼灼術(RFA)などの局所療法を行うことがあります。
薬物療法
切除の難しい膵・消化管原発のNETでは、薬物療法が行われます。ホルモン症状の有無、腫瘍の悪性度や肝病変の程度、併存疾患により薬剤は使い分けがされます。
- ソマトスタチンアナログ(オクトレオチド、ランレオチド)
ホルモン症状を緩和するとともに抗腫瘍効果も証明された薬です。オクトレオチドは消化管NETに、ランレオチドは、膵と消化管NETに対して保険適応となっています。4週に1回 おしりに皮下注射を行います。 - エベロリムス
mTORを標的とした分子標的薬です。膵・消化管NET以外にも肺、原発不明のNETに対しても使用されています。 - スニチニブ
スニチニブは血管新生増殖因子受容体を特異的に阻害する分子標的薬です。2021年時点では、膵NETにのみ保険承認されています。 - ストレプトゾシン
膵と消化管NETに対して保険承認されている点滴で用いる薬です。6週ごとに5日間連続で投与する方法と毎週投与する方法があります。 - 放射線核種標識ペプチド治療(Peptide receptor radionuclide therapy:PRRT)
SSTR(ソマトスタチン受容体)を標的とした放射線内用療法です。ルテチウムオキソドトレオチド(177Lu)が2021年に保険承認され、日本でもPRRTを行うことが可能になりました。ソマトスタチン受容体陽性の神経内分泌腫瘍が適応となっており、オクトレオスキャン検査で腫瘍に集積を認めたNET患者さんが治療対象とされています。
神経内分泌癌(NEC)の治療
NECの手術適応については明らかにされておらず、慎重に判断する必要があります。
転移を伴う膵・消化管のNECに対してはプラチナ系薬剤を含む併用療法(エトポシド+シスプラチン療法もしくはイリノテカン+シスプラチン療法)が行われます。腎臓が弱っている方や体力の低下した方ではエトポシド+カルボプラチン療法が行われることがあります。
肉腫(サルコーマ)について
肉腫(サルコーマ)とは
がんは、上皮から発生する比較的頻度の高い癌腫(胃癌、大腸癌、肺癌、肝癌、乳癌、子宮癌など)は良く認知されていますが、頻度が低い(人口10万人に対し、6人以下)上皮以外の骨、軟骨、脂肪、筋肉、末梢神経、線維組織、血管などの非上皮性組織から発生するがんを、肉腫(サルコーマ)と呼んでいます。上皮は臓器の表面を覆う組織で、常に外界からの刺激に晒されているため遺伝子の損傷頻度が非上皮性組織に比べ、高いことなどの要因で癌化しやすいと考えられています。骨、筋肉、末梢神経などを扱う整形外科領域では、特に四肢に発生するがんは転移したのもを除いて、ほぼ肉腫であるため整形外科が担当することが多い領域ですが、子宮や後腹膜、乳房、内臓器にも稀に発生することがあり、その診断、治療には多科連携による集学的アプローチが必要な領域とされています。また整形外科領域では、診断や治療様式の違いから、肉腫を骨や軟骨から発生する肉腫と、軟部組織(脂肪、筋肉、末梢神経、線維組織など)から発生する軟部肉腫に大きく分類しています。
主に四肢に発生する軟部肉腫について
症状と診断
上肢、下肢、或いは背中、胸壁などに発生する軟部肉腫は体表に近いため、多くの場合局所の腫脹として気付きます。肉腫の場合一般的に月単位で次第に大きくなりますが、悪性度が低いものでは年単位の場合もあります。疼痛は炎症が強いケースや、神経から発生したもの、また肉腫に隣接する神経を巻き込むものでは認められますが、無痛であることも稀ではありません。 このような腫瘍を認めた場合、行う検査としてはMRIで発生部位や性状を調べた後に、針生検や切開生検により組織診断を行います。軟部肉腫は稀な疾患ですが、病理分類は30種類以上に亘るため、確定診断には専門性が要求されます。
進行度と治療について
軟部肉腫の診断がつけば、PET-CTや造影CTで転移の有無について検索します。転移は殆どのケースで肺に認められ、横紋筋肉腫、粘液型脂肪肉腫など組織型によってはリンパ節転移や肺以外の様々な部位に転移する場合があります。転移が無い場合とある場合で治療は異なってきます。
転移が無い場合:
基本的に手術で切除しますが、腫瘍のみの切除では再発するリスクが非常に高いため、周囲の組織をある程度含めて切除する広範切除術を行います。その際に必要な皮膚や血管の欠損が生じた場合は移植術を併用する場合があります。また再発をさらに抑えるため、術後に放射線を照射する場合もあります。転移発生のリスクを下げる目的で、術前や術後に化学療法を併用する場合もあります。
転移がある場合:
診断時に転移が認められた場合、基本的には局所の切除術は施行せず、化学療法や放射線療法を行います。最近軟部肉腫に保険適応をなった薬剤の種類が増え、転移した場合でもある程度の効果を認めています。転移を認めた場合でも、摘出によるメリット、デメリットを評価したうえで切除術を検討することがあります。
後腹膜腔に発生する肉腫について
症状と診断
後腹膜腔とは、腹膜腔の背側で、腸管が存在する膜腔の後壁との間のスペースで、腎臓や尿管、大動静脈などの臓器の一部や腸腰筋、腰神経叢などがある場所です。脂肪組織が豊富で脂肪肉腫の好発部位でもあります。この部位は体表からは触れず、ある程度大きくなるまで気付かないため、初診の段階で巨大な腫瘍を形成していることが稀ではありません。PET-CT、MRIを施行し、可能であれば針生検を行い、組織診断を行います。
治療について
巨大な腫瘤を認める場合でも、転移していないことが多く、発生部位が泌尿器科、婦人科、消化器外科、整形外科などの領域に亘るため、手術、放射線治療、化学療法を組み合わせた治療を放射線科や病理医を含めた多診療科で検討します。手術や放射線療法が困難なケースでは化学療法が選択されます。
子宮肉腫について
動向
肉腫とは、骨や、筋肉、脂肪、血管などの軟部組織から発生する悪性腫瘍です。“がん”と比べて発生頻度が低いため十分な研究がなされておらず、診断や治療が難しい病気です。婦人科臓器では主に子宮の筋肉や支持組織から発生します。
子宮肉腫は子宮に発生する悪性腫瘍の約3-7%を占めるにすぎず、その中でも子宮平滑筋肉腫の頻度が高い。悪性度は非常に高く、生存期間の中央値は5年も満たない状況です。
症状と診断
子宮肉腫の症状は腹部膨満感や不正出血など、特異的な症状ではありません。子宮筋腫との区別が難しく、閉経後に子宮の腫瘤が急激に大きくなるなどの臨床経過や子宮筋腫として手術を行った後に病理検査で診断が判明することも珍しくありません。したがって、エコーやMRIで肉腫の疑いを指摘されることがありますが、最終的には摘出された病変の病理検査で診断される場合がほとんどです。
子宮肉腫の中には良・悪性の判定も困難な症例が存在し、日常診療では診断に苦慮することが多々あります。
進行度(ステージ)と治療について
以下の進行期は子宮肉腫の中で、子宮平滑筋肉腫/子宮内膜間質肉腫の進行度(ステージ)です。
| I期 | 腫瘍が子宮に限局する |
|---|---|
| Ⅱ期 | 腫瘍が骨盤腔に及んでいる |
| Ⅲ期 | 腫瘍が骨盤外に及んでいる |
| Ⅳ期 | 腫瘍が膀胱、直腸の粘膜に及ぶか遠隔転移している。 |
治療については外科的切除(手術)、抗がん剤、放射線を組み合わせて行われます。
手術について:子宮平滑筋肉腫に関しては手術による摘出が最も効果的な治療法です。病巣を完全に摘出することが目標ですが、摘出時で腫瘍を細切する方法は再発を誘発するので勧められません。
低異型度子宮内膜間質肉腫では、ホルモン治療に有効なことがあるため、機能温存手術などの検討が模索されています。
抗がん剤治療:子宮肉腫に対して使用される最も一般的な抗がん剤はドキソルビシン、イホマイドやドセタキセル、ゲムシタビン療法です。進行例や再発時にはパゾパニブ、トラベクテジン、エリブリンなどが使用されることもあります。
悪性中皮腫について
動向
中皮とは胸であれば肺や心臓、お腹であれば胃や腸などの臓器を覆ている膜の事です。この膜から発生したがんが『悪性中皮腫』です。肺を覆う『胸膜』から発生する、『悪性胸膜中皮腫』が最も多い中皮腫で、アスベスト(石綿)の吸入が一因になります。
悪性中皮腫による死亡者数は年間1500人を超え、増加傾向にあります。アスベストは2012年から全面的に使用が禁止されていますが、それまでに使用された建築物などは現存しています。加えて、アスベスト曝露から悪性中皮腫の発生までが平均で40年程度と長い事から、2025年ごろまでは患者数が増え続けると言われています。
症状と診断
悪性中皮腫は早期にはほとんど症状がありません。進行すると、悪性胸膜中皮腫では胸水、悪性腹膜中皮腫では腹水が貯まり、それぞれ、呼吸困難感や腹部膨満感などの症状が出てきます。
診断は胸水や腹水を検査することで得られることもありますが、正確な診断のためには、組織の一部を採ってくる『生検』が行われます。生検の方法はエコーやCTを見ながらの針生検か手術によるものが一般的です。
生検によって得られた組織は、病理検査で『上皮型』、『二相型』、『肉腫型』に分類されます。この分類は治療方針の決定に重要です。
進行度(ステージ)と治療について
以下は中皮腫の中で、大多数を占める『悪性胸膜中皮腫』について述べます。
進行度(ステージ)については、国際中皮腫会議(IMIG)による分類が一般的です。
| I期 | 腫瘍が片方の中皮のみにある |
|---|---|
| Ⅱ期 | 腫瘍が片方のみの中皮から肺や横隔膜に及んでいる |
| Ⅲ期 | 腫瘍が片方の中皮全体から心臓の膜など切除の可能性が残る部位に及んでる |
| Ⅳ期 | 腫瘍が胸壁(肋骨とその間の筋肉)や反対の胸膜、リンパ節などの切除不能な部位に及ぶか胸腔外(腹部や骨、頭部など)に転移している。 |
治療については外科的切除(手術)、抗がん剤、放射線を組み合わせて行われます。
手術について:手術は多くの場合、病理検査で『上皮型』と診断された場合にのみ行われます。また、手術の効果自体がはっきりしていない点も多く、手術するか否かについては、経験のある呼吸器外科医と呼吸器内科医の総合的な判断が必要です。
手術には片方の肺と胸膜を切除する『胸膜肺全摘術』と、胸膜だけを剥ぎ取る『胸膜剝皮術』があります。胸膜肺全摘術は大きな手術になりますので、体力的に耐えられる例に限られます。胸膜剝皮術は比較的新しい手術法です。胸膜肺全摘術と胸膜剝皮術のどちらが優れているかについては、まだ明確なデーターはありません。
手術後は、胸膜肺全摘術後には放射線+抗がん剤、胸膜剝皮術については抗がん剤の補助療法が行われます。
抗がん剤治療:悪性胸膜中皮腫に対して使用される最も一般的な抗がん剤はペメトレキセドとシスプラチンです。抗がん剤が効果を示さなくなってきた(がんが増大してきた)場合には免疫チェックポイント阻害薬が使用されることもあります。
補足
中皮腫の患者さんには、公的補助制度があり、医療費の補助されます。アスベストに曝露される仕事に従事されていた方に対する労働災害認定(労災)の申請と、労災に認定されなかった患者さんに対する石綿健康被害救済法に基づく申請です。
消化管間質腫瘍 (Gastrointestinal Stromal Tumor:GIST)について
GISTは、消化管の粘膜下にある間葉系細胞由来の腫瘍です。罹患率は10万人当たり1人程度と稀な腫瘍で、胃、次いで小腸に多くみられます。性差はなく、発症年齢の中央値は60歳とされています。
症状と診断
GIST特有の症状はありません。腫瘍が大きくなると腹痛、吐き気、下血、吐血、貧血などの症状が出現することがあります。胃のGISTの半数以上は無症状とされています。
診断には、内視鏡検査、CTやMRI、PET-CTなどの画像検査を行い、腫瘍の大きさや転移有無、浸潤の程度を確認します。また腫瘍組織の免疫染色を行い、KIT陽性あるいはDOG1陽性の場合GISTと診断されます。組織採取は、腫瘍の皮膜を傷つけないように細心の注意が必要です。
悪性度の評価について
GISTの悪性度の評価は、腫瘍の大きさ、顕微鏡で50視野あたりの核分裂像数、発生臓器、腫瘍破裂の有無によりModified Fletcher分類を用いて行われます。高リスクGISTでは完全切除されても再発のリスクが高いとされています。
原発部位が胃の場合
| リスク分類 | 腫瘍径(cm) | 核分裂像数 ( / 50視野) |
腫瘍破裂の有無 |
|---|---|---|---|
| 超低リスク | ≤2.0 | ≤5 | なし |
| 低リスク | 2.1-5.0 | ≤5 | |
| 中リスク | ≤5.0 | 6-10 | なし |
| 5.1-10.0 | ≤5 | なし | |
| 高リスク | あり | ||
| >10.0 | なし | ||
| >10 | なし | ||
| >5.0 | >5 | なし |
原発部位が胃以外の場合
| リスク分類 | 腫瘍径(cm) | 核分裂像数 ( / 50視野) |
腫瘍破裂の有無 |
|---|---|---|---|
| 超低リスク | ≤2.0 | ≤5 | なし |
| 低リスク | 2.1-5.0 | ≤5 | なし |
| 高リスク | あり | ||
| >5 | なし | ||
| >5.0 | なし |
治療について
GISTと診断もしくはGISTが強く疑われる場合、原則的に外科切除を行います。組織採取のできない小さな腫瘍や症状のない場合には経過観察となることがあります。高リスクGISTでは、手術後、3年間のイマチニブ治療が標準治療とされています。
手術が難しい場合や他臓器への転移を有する場合は、薬物療法が適応となります。
薬物療法
イマチニブが切除不能、転移・再発性GISTに対する標準治療とされています。イマチニブ耐性のGISTに対しては、スニチニブによる2次治療が標準治療とされています。さらにスニチニブ耐性のGISTにはレゴラフェニブによる3次治療が標準治療とされています。
これらの薬剤は分子標的薬と呼ばれるものですが、皮膚毒性、循環器毒性、内分泌・代謝に関わる毒性などが知られています。そのため治療中は多職種によるチーム医療が必要になります。