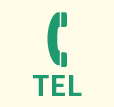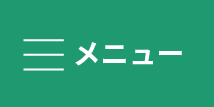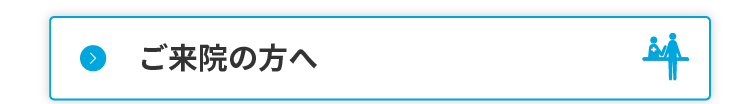疫学
日本における腎がん(上部尿路がん含む)の推定罹患率は、2014年で人口10万人あたり男性:27.6人、女性:12.7人と報告されています(国立がん研究センターがん対策情報センター)。この罹患率は男女ともに年々増加しています。男女比は約2:1で男性に多く、高齢になるほど発生頻度も高くなります。一方、腎がんによる死亡率は人口10万人あたり男性で9.9人、女性で5.4人です(2017年)。がんと聞けば肺がんや胃がん、女性では乳がんを思い浮かべる方が多いと思いますが、泌尿器科系悪性腫瘍の中では、前立腺がん、膀胱がんに次いで多い腫瘍です。
腎がん発生の危険因子として、喫煙、カドミウムやアスベストなどの職業による暴露、肥満が知られています。また、慢性血液透析患者の30-50%に後天性嚢胞性疾患が発生しま すが、この疾患では通常に比べ腎がんの発生率は30倍にも上昇します。その他にも腎がんと関連する基礎疾患として、von Hipple-Lindau(フォンヒッペル・リンドウ:VHL)病などがあります。
- -参考-
- VHL病:1900年代初めドイツの眼科医von Hippelによって網膜の血管芽腫が報告され、その後スウェーデンの病理学者Lindauが40例を集めて報告、VHL病と命名されました。 網膜の血管芽腫と小脳・脊髄の血管腫、腎・肝・膵などに多彩な病変(嚢胞・血管腫・腺がん)を合併することで有名です。腎がんの合併は35-83%とされています。
診断
腎がんの臨床症状として古典的3主徴が有名です。これは、血尿、腹部腫瘤、疼痛(腰背部痛)のことですが、現在診断される腎がんでこの3主徴が揃うのはわずか数%で、70%以上の腎がんは偶発がんです。偶発がんとは、症状がなく発見される腎がんのことで、たとえば人間ドックで行った超音波検査で偶然発見された、などのケースです。ただし、腎がんでは無症候性顕微鏡的血尿が約40%に見られ、血尿精査で施行するCTや超音波検査で見つかることも多いのです。偶発がんの多くは小さな腫瘍であるため、症状があって見つかる腎がんより予後がよいことが知られています。
腎がんに付随する症状として発熱があり、これは約20%に見られます。その他の全身的症状として、体重減少、貧血、肝障害、高カルシウム血症などがあります。これらの症状は、一般にがんが進行すると出現してきます。
腎がんの診断は、造影CTによりほとんどの場合可能です。最近のマルチスライスCTによってダイ ナミック(動脈相)および静脈相の撮影を行えば診断がつきます(図)。

その他の画像診断として、MRIや超音波検査があります。CTだけでは診断できなかった場合などに他の検査と組み合わせてより正確な診断ができるようにしています。ただ、腫瘍径が4cm以下と小さい場合は、良性腫瘍の頻度が高くなるため注意が必要です。手術前に腎がんと診断して手術を行っても、10%程度に良性腫瘍が含まれることがわかっています。PET/CTは腎がんの診断にはあまり使用されません。これはPETで使用する検査薬(FDG)が腎で排泄されるため、正常腎にも集積があるため診断が困難であるためです。また、CTの精度が悪かった時代には血管造影が必須とされていましたが、前述の通り、マルチスライスCTやMRIの登場によりその必要性はなくなりました。現在では逆にCTやMRIから血管の構築ができるようになっています(図)。

3次元画像解析(ヴィンセントの画像)について最近の画像解析は血管の構築だけでなく、腫瘍や正 常腎、尿路の画像も表示できるようになりました。右の図がその例です。この画像を見ると血管の走行や腫瘍の位置関係が正確にわかります。この画像解析は腎部分切除術の適応になる小さな腫瘍でさらに威力を発揮します。腫瘍に入っている血管を腫瘍近くまで同定できたり、腫瘍自体を画像から消して腫瘍の切除ラインを決定したりできます。このことで手術のシミュレーションがより正 確にできるようになったのです。また、一度画像の構築が終了すると画像を回転させて自分が見たい方向から見ることもできます。

良性腫瘍が疑われる場合、腫瘍生検を行うことがあります。生検での診断効率は、約70%とされていますが、実際に生検を行うケースは非常に少ないです。画像診断が進歩したために必要性が少なくなったことに加え、生検による出血や腫瘍の播種をおそれてのことですが、実際には合併症はほとんど起こっていません。最近、小さな腫瘍や多発する腫瘍に対して凍結療法やラジオ波焼灼術による治療が行われるようになり、この場合には治療前に腫瘍生検が施行されます。
臨床病期
がんの進行度にはTNM分類がよく使用されます。T:原発腫瘍(腎の状態)、N:リンパ節、M:転移を意味します。TNM分類は時々改訂され新しくなりますが、現在最も新しい分類は2017年の改定版です。以下に2017年TNM分類を示します。
1.T分類
- T1:がんが腎被膜内で、かつ最大径7cm以下
- T1a:腫瘍が4cm以下
- T1b:腫瘍が4cm< ≦7cm
- T2:がんが腎被膜内で、最大径7cmを超え、腎に限局
- T2a:腫瘍が7cmを超えるが10cm以下
- T2b:腫瘍が10cmを超え、腎に限局
- T3:がんが主静脈あるいは腎周囲組織に進展しているが、同側副腎への伸展がなくゲロータ筋膜(腎筋膜)内にとどまるもの
- T3a:肉眼的に腎静脈内に伸展あるいは腎周囲、腎門部組織への浸潤
- T3b:下大静脈へ進展するが横隔膜を超えない
- T3c:横隔膜より上の下大静脈への進展あるいは下大静脈壁への浸潤
- T4:がんがゲロータ筋膜を越えて浸潤。同側副腎への直接進展
2.N分類
- N0:リンパ節転移なし
- N1:所属リンパ節転移
3.M分類
- M0:遠隔転移なし
- M1:遠隔転移有り

病期分類 |
T分類 |
N分類 |
M分類 |
|---|---|---|---|
ステージ1 |
T1 |
N0 |
M0 |
ステージ2 |
T2 |
N0 |
M0 |
ステージ3 |
T3 T1-3 |
N0 N1 |
M0 M0 |
ステージ4 |
T4 Tに関わらず |
Nに関わらず Nに関わらず |
M0 M1 |
病理組織学的分類
腎がんには様々なタイプがあり、それぞれに特徴を持っています。
1)淡明細胞がん
腎がんの75-85%を占めています。von Hippel-Lindau (VHL)病に発生する腎がんはこのタイプです。このVHL病から発見されたVLH遺伝子はその後の研究で、自然発生腎がんにおいても40-50%で異常が認められることがわかりました。
2)乳頭状腎細胞がん
腎がんの10-15%を占め、VHL病以外の家族内発生(遺伝)に多いタイプです。また、最近の研究でタイプ1とタイプ2に細分類されており、タイプ2の予後は悪い事が知られています。
3)嫌色素性細胞がん
腎がんの5-10%を占め、一般に予後良好とされています。
4)紡錘細胞がん
頻度は非常に少ないのですが予後不良です。
5)その他のタイプ
嚢胞随伴性腎細胞がんや集合管がん(ベリニ管がん)などがあります。集合管がんは紡錘細胞がん同様非常に予後不良です。
予後
腎がんの予後(5年生存率)はⅠ(1)期で95%以上、Ⅱ(2)期で75-95%、Ⅲ(3)期で59-70%、Ⅳ(4)期では約20%とされています。腎がんの特徴として、10年以上経過しても再発転移を来たし、がん死する症例があることが知られています。臨床病期以外の予後因子としては、組織学的悪性度(grade)があり、悪性度が高いほど予後は悪くなります。腎がんの組織型による予後の差はないとされていますが、紡錘型とベリニ管がんは別格でこれらの予後は悪いです。その他の予後に関連する因子として、全身状態(PS)や症状の有無(血尿など)、発熱、貧血などがあります。